サクラサク

卒業シーズン、入学シーズンを象徴する背景画像といえば、きまって満開の桜。そしてBGMは「桜ソング」。サクラは万葉集や古今和歌集でも詠まれているほど、古くから日本で愛され続けてきた花です。サクラといえば日本をイメージするほど、今や世界でも有名になりました。でもサクラは北半球の温帯地域に広く分布し、鑑賞に適した種類や実を収穫する種類、常緑の種類など、さまざまな種類が見られます。今回は美しい花が楽しめる日本のサクラについて紹介します。

サクラの種類はどれくらいある?
サクラは、バラ科サクラ亜科サクラ属の落葉高木、または低木です。日本ではヤマザクラ、オオヤマザクラ、カスミザクラ、オオシマザクラ、エドヒガン、チョウジザクラ、マメザクラ、タカネザクラ、ミヤマザクラ、クマノザクラの10種を基本にして、変種を合わせると100種以上の桜が自生していて、沖縄には野生化したカンヒザクラがあります。また、これらから育成された園芸品種は200以上もあり、一重咲きや華やかな八重咲き、枝垂れ咲きなど、品種によって多様な咲き姿や色合いを楽しむことができます。

その中でも、江戸末期~明治初期頃から園芸品種として栽培されていて、当時の染井村の植木職人や造園師が、オオシマザクラとエドヒガンを交配させてつくったとされている「ソメイヨシノ」は日本固有の桜として最も有名です。このソメイヨシノの片親の「エドヒガンザクラ(江戸彼岸桜)」は、寿命が長いことが特徴で、日本の三大桜といわれ、国の天然記念物に指定されている山梨県北巨摩郡武川村の山高神代桜(やまたかじんだいざくら)は樹齢2,000年以上、岐阜県本巣市の根尾谷淡墨桜(ねおだにうすずみざくら)は樹齢1,500年以上、福島県田村郡三春町の三春滝桜(みはるたきざくら)は樹齢1,000年以上など、いずれもこのエドヒガンザクラです。

花見の起源
最初の花見は桜ではなく、奈良時代にはじまった梅の花見だったという話は有名です。この風習は中国との交流が盛んになる中で日本にやってきたもので、貴族たちの間では庭に梅を植えるのが流行していたと言われています。この貴族の花見が鎌倉時代になり武士にも広まり、中でも豊臣秀吉により行われたもので、徳川家康などの有名な武将を総勢5000人招いた「吉野の花見」と、醍醐(だいご)寺に700本もの桜を植えて行われた「醍醐の花見」が歴史に残るもっとも盛大なお花見だと言われています。その後に江戸時代になり、庶民の間でもお花見が楽しまれるようになりました。

お花見のルーツについては、他にも古代の桜は御神木として大事にされ、開花はその年の作柄を教えてくれるものとして、人々は豊作を占うために花見をしてきたという説もあり、昔から行われている花見は山に咲くヤマザクラを見るのが主流で、後に宮人や貴族の「花の宴」へと移り、8代将軍・徳川吉宗によって現在のお花見の風習が確立したという流れをたどっています。

いかがでしたでしょうか、今回のサクラの話題。日毎に少しずつ暖かくなる季節になると、やっぱり桜を見たいという気持ちが高まりますよね。2021年のお花見はコロナ禍で多くのお花見スポットで飲食禁止になったり、企業やサークルなどグループでの宴会を自粛したり、夫婦や恋人同士で散歩しながらのお花見といった近場で&家族など身近な人と、こぢんまりと小人数でという、「安・近・小」のお花見スタイルでした。さてコロナ終息の兆しが見え始めた今年のお花見をあなたはどんなスタイルで楽しみますか?




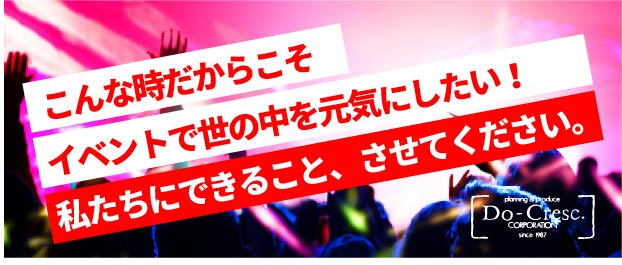


この記事へのコメントはありません。